

全社横断の AI チームを結成し、生成 AI の可能性を探る
コニカミノルタは、祖業であるカメラ、フィルムから培ってきたイメージング技術を核としながら、さまざまな分野で事業を展開するグローバル企業です。2023 年に創業 150 周年を迎えた同社では、ものづくり企業としての DNA を脈々と受け継ぎながら「世界中のお客様の“みたい”という想いに応え、人々の生きがいを実現する」ことに挑戦してきました。
コニカミノルタ株式会社 執行役員 技術開発本部長の岸 恵一 氏は、生成 AI の可能性についてこう語ります。
「私たちのコア事業であるイメージング事業では、生成 AI の登場以前から画像処理系の AI 活用に取り組んでおり、AI の有用性は広く理解していました。また当社は、新たな技術の開発や新たな領域への進出に意欲的な社風を持っており、経営陣も生成 AI は挑戦に値する技術だと捉えています。そのような背景から、新しい価値を生み出すツールとして生成 AI には大いに期待しています
全社横断の生成 AI チームが結成されたのは 2023 年 7 月。さまざまな部門に所属する生成 AI の活用意欲を持つ人財と、彼らを技術的な面でカバーするために集められた、セキュリティ、クラウド、プログラミングなどの得意分野を有する IT 人財、あわせて 30 名ほどで構成されています。
「まずは生成 AI をどのように活用できるのかを、少人数のチームでフラットに話し合える場を用意しました」と語るのは、横断チームの発案者であるコニカミノルタ株式会社 技術フェロー 技術開発本部 技術担当の奥田 浩人 氏。生成 AI を使ってどのようなことをしてみたいのか。それを実現するにはどのような技術が必要なのか。そしてその際にどのような問題が生じるのかといった議論が行われ、できることの骨格を少しずつ形成していったそうです。
同時に AI 利活用におけるガバナンスの機動的な確立も進め、「コニカミノルタグループAIの利活用に関する基本方針」をベースに、生成 AI を活用する際のガイドラインを定めました。
「Microsoft の「責任ある AI の原則」も参考にしながら、AI の使い手である私たちとしての責任についての議論を積み重ねて、実際に生成 AI プロジェクトの検証を進める過程のなかでガイドラインをアップデートしていきました」(奥田氏)

私たちはこれまでの 150 年の歴史のなかで、さまざまな技術を活用してサービスをつくり出し、お客さまに提供してきました。生成 AI についても、いずれは当たり前の技術として事業のなかで活用していきたいと考えています
岸 恵一 氏, 執行役員 技術開発本部長, コニカミノルタ株式会社

生成 AI 活用の開発基盤として Azure OpenAI Service を採用
こうして活用方法とガバナンス強化の議論が進み、生成 AI の使い方が見定められたことで開発が進められたのが、社内技術情報検索アプリ「技術資産 AI-Chat」と研究支援ツール「EDISON(Experimental Data Integrated Solution On the Network)」です。そしてこれらの開発ツールとして採用されたのが、Microsoft のクラウド AI サービス「 Azure OpenAI Service(AOAI)」でした。
導入にあたって同社では、日本マイクロソフトが主催する AOAIのハンズオン セミナーに参加。日本マイクロソフトのパートナー企業であり国内随一の AOAI 導入実績を誇るゼンアーキテクツ社のエンジニアから、生成 AI を用いて自社データを活用する基礎を学んだそうです。
ハンズオン セミナーでは、AOAI とともに統合 AI データベース「Azure Cosmos DB」や生成型 AI 検索サービス「Azure AI Search」といった Azure の 製品・サービスの機能を学んだうえで、実際に AOAI を使って自社データを検索するアプリを制作するというプログラムが提供されました。
ハンズオン セミナーには横断チームの組込みエンジニアからAIエンジニアまで、幅広い層の開発者が参加しました。横断チームの一員であり、Azure のクラウドエンジニアであるコニカミノルタ株式会社 技術開発本部 研究戦略センター 企画推進部 アシスタントマネージャーの児玉 祥紘 氏はセミナーをこう振り返ります
「AOAI とその周辺サービスを組み合わせることで、こんなに簡単にアプリが作成できてやりたいことを実現できるのかと驚きました。RAG(Retrieval-Augmented Generation)の最新アーキテクチャなども教えていただけたので、開発の目処を立てることができました」(児玉氏)

AOAI を導入した理由は、まず私たちが検討を開始した 2023 年7月の段階で最も進んだ AI モデルの作成環境であったこと。それから業務インフラとして多くの利用実績があったこと。そして Microsoft が”責任ある AI の原則”で安全性やガバナンスに関するスタンスを明確にしていたことです
奥田 浩人 氏, 技術フェロー 技術開発本部, コニカミノルタ株式会社

情報資産を有効活用するために AOAI によって検索アプリを開発
ものづくり企業である同社が常に抱えてきた課題のひとつに、技術資産の継承があります。150 年の歴史を誇り幅広い領域で事業を展開する同社では、社内の膨大な技術や知識が散在しています。これらの情報を収集、保存して効率的に利用することが研究支援につながると考えたのが、コニカミノルタ株式会社 技術開発本部 技術戦略統括部 戦略推進部 技術強化グループ アシスタントマネージャーの渡邊 美音 氏でした。
社内技術を知りたいと思ったときに、関連すると思われる論文をテクノロジーレポートから検索して内容を把握するのは手間も時間もかかります。渡邊氏は、AI が内容を読み込んで提示する検索アプリの開発を、横断チームの定期勉強会でメンバーに相談しました。
相談を受けた児玉氏によると、学んだ知識とツールを使えば検索アプリ自体はすぐに構築できると感じたそうです。
「技術的にはそれほど難しくない反面、社内での AOAI による開発事例がなかったために、本当にセキュアな環境で開発できるのか、技術資産を社内公開することに問題はないのかといったガバナンスの精査に神経を使いました」(児玉氏)
セキュリティのスペシャリストであるコニカミノルタ株式会社 IT 企画部 ビジネスエンゲージメントグループ エキスパートの福谷 優 氏も、この提案を AOAI のセキュリティを試す機会として捉えたそうです。
「初めての開発環境ですから、どこにどんな脅威が潜んでいるかわかりません。脅威分析モデル STRIDE を使って、児玉と連携しながら一つひとつ脅威を洗い出したうえで、脅威が顕在化するリスクをゼロに近づけるべく、対策を実施しました。AOAI でも STRIDE モデルが有効なことは理論上わかっていたのですが、実際のアプリ制作でそれを証明できたことは、今後の開発に向けてポジティブな成果だと考えています。最終的には、得られた知見を当グループの情報システム機能会社である”コニカミノルタ情報システム(HJS)”のメンバーにも伝えられたのは大きな成果。グループ全体に拡大してほしいと考えています」(福谷氏)

今後は、テクノロジー レポートに掲載されていない技術情報の格納や人財報の強化を検討していきます。そのような形でデータを増やせれば、詳細な技術情報の検索ができたり、実際に技術に詳しい人財と技術を求める人とのマッチングを図れたりと、さらに活用の幅が広がると考えています
渡邊 美音 氏, 技術開発本部 技術戦略統括部 戦略推進部 技術強化グループ, コニカミノルタ株式会社
大きな反響を得た社内技術情報検索アプリ「技術資産 AI-Chat」
こうして開発されたのが社内技術情報検索アプリ「技術資産 AI-Chat」です。渡邊氏の構想に基づいて 2023 年の秋から仕組みを検証、2024 年の年初から開発に着手し、3 月末にリリースを迎えました。
「役員会議でデモを行ったところ、私の体感では過去 1 年間で最も大きな反応がありました」と岸氏が言うとおり、社内での期待値も膨らんでいます。
「今後は、テクノロジー レポートに掲載されていない技術情報の格納や人財報の強化を検討していきます。そのような形でデータを増やせれば、詳細な技術情報の検索ができたり、実際に技術に詳しい人財と技術を求める人とのマッチングを図れたりと、さらに活用の幅が広がると考えています」(渡邊氏)
「問い合わせのログも溜まっていますので、技術戦略統括部ではその内容を Microsoft Power BI で可視化・分析を始めており、他社に遅れを取らないように今後の施策に反映するための構想を練っています」と意欲を見せる児玉氏。福谷氏も「人財マッチングの運用を考えると、機微情報である人事データの扱い方に留意する必要があります。セキュリティ担当として適切に対応していければ」と次のフェーズを見据えています。

AOAI とその周辺サービスを組み合わせることで、こんなに簡単にアプリが作成できてやりたいことを実現できるのかと驚きました
児玉 祥紘 氏, 技術開発本部 研究戦略センター 企画推進部, コニカミノルタ株式会社

研究データを共有、有効活用するための研究支援ツール「EDISON」
今あるデータを有効に活用するためのツールが「技術資産 AI-Chat」であるとすると、これから生み出されるデータを有効活用するための基盤となり得るのが、研究支援ツール「EDISON(Experimental Data Integrated Solution On the Network)」です。
EDISON を考案し、自ら構築したのは、入社 2 年目のコニカミノルタ株式会社 技術開発本部 デバイス技術開発センター マテリアル・デバイス開発部 技術価値検証グループ、野場 考策 氏でした。
野場氏によると、自身の所属する技術開発本部では、日々の実験を記録するために紙の実験ノートが使われていたり、記録データを各々の PC に保存したりといった状況でした。決まったフォーマットもなく、書き方は個人に任されていたそうです。
「皆さん記録は残すのでデータは蓄積されますが、保存の仕方がバラバラなので極めて共有しにくい状況でした。そもそも部内ではさまざまな研究が並行して行われていますから、隣の同僚がどんなテーマで研究しているのかわからないといった事象も発生していました」(野場氏)
そこで野場氏は、まず共通の電子実験ノートの導入を進言し、ツールの選定と導入を担当しました。さらに「記録するだけでは意味がない」と、実験記録を要約、共有するシステムとして「EDISON」を考案したそうです。
プログラミング経験ゼロからでもスムーズに扱える AOAI
「EDISON」は、電子化された実験ノートの内容を Azure OpenAI を用いて要約し、Microsoft Teams を介してチームメンバーに通知するシステムです。RAG による実験内容の検索にも一部対応しています。もともとプログラミングの経験はほとんどなかったという野場氏ですが、EDISON のプロトタイプは 3 週間ほどで構築できたそうです。
「入社時に研修でプログラミングやクラウドについて学んだ経験から、ある程度の基礎を持っていたのが大きかったと思っています。ハンズオン セミナーの録画を見て、AOAI について学ぶこともできました。AOAI は非常に操作性がよく、私のような初学者でもスムーズに扱えました」(野場氏)
EDISON はすでにユーザーが 100 名を超えており、次のフェーズとしては既にバイオ研究者向けの雑誌に電子実験ノートの取り組みを発表しており※、社内外の要望のあった事業部への横展開を検討しています。
「新しいシステムは、ともすればこれまでの方法に馴染んでいる人から反発されてしまう可能性もあるので、横断チームの皆さんから周囲に広めていただく形で、納得感を持って受け入れてもらえるような展開の仕方を考えています」(野場氏)

AOAI でも STRIDE モデルが有効なことは理論上わかっていたのですが、実際のアプリ制作でそれを証明できたことは、今後の開発に向けてポジティブな成果だと考えています
福谷 優 氏, IT 企画部 ビジネスエンゲージメントグループ, コニカミノルタ株式会社
次の 150 年に向けて、生成 AI の技術を当たり前のものにしていく
「ある程度の成果はあったものの、全社の全職種が活用するに至ったかというとまだ道半ば」とこの 1 年間を振り返る奥田氏。「これまでは“まずは使ってみる”というフェーズでしたが、今年は生産性向上や収益改善といった眼に見える成果につなげる年にしていきたい」と展望を語ります。
「もうひとつ大切なのは、取り組みを継続することです。この取り組みは次第に定常的な状態になっていくとは思いますが、まだしばらくは横断チームの熱量を保ち続けるための仕掛けに取り組んでいきたいと考えています」(奥田氏)
そのためには、日本マイクロソフトにもサポートをお願いしたいと奥田氏。「AOAI は、まだ初学者が安心して使いこなすにはハードルが高いツールだと感じています。日本マイクロソフトさんには、ドキュメントを増やしていただくなど、さらに使いやすいものにしていただけるとありがたいです」(奥田氏)
これまで長く Azure に触れてきた児玉氏は、日本マイクロソフトならではの AI 活用ソリューションに期待を寄せます。「技術資産 AI-Chat の開発をスムーズに進められたのは、Microsoftが使いやすくて優秀な PaaS 群を世に出してくれていたおかげだと思っています。これから先もクラウド、生成 AI のトップ ランナーとして走り続けてくれることを期待しています」(児玉氏)
最後に岸氏は、「生成 AI はあくまでツールであり、それを使ってどのようにお客さまの課題、自分たちの課題を解決するかが重要」と、目的と手段を混同しないことの大切さについての言葉がありました。
「私たちはこれまでの 150 年の歴史のなかで、さまざまな技術を活用してサービスをつくり出し、お客さまに提供してきました。生成 AI についても、いずれは当たり前の技術として事業のなかで活用していきたいと考えています。これから先の 150 年もお客さまのご期待に応え続けていけるように、日本マイクロソフトさんと共に技術を深めていきたいと思っています」(岸氏)
全社横断の生成 AI チームによる生成 AI 活用の機動的推進を通していち早く生成 AI を社内に普及し、新たな価値を生み出そうとしているコニカミノルタ。私たち日本マイクロソフトもそのスピード感に対応し、よりよいご支援を届けられるように努力してまいります。
※参考文献 村西和佳,野場考策
"第167回 電子実験ノートeLabFTWと生成AIを活用したLabDX"
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/opinion/vol42n8.html

AOAI は非常に操作性がよく、私のような初学者でもスムーズに扱えました
野場 考策 氏, 技術開発本部 デバイス技術開発センター マテリアル・デバイス開発部, コニカミノルタ株式会社

関連の事例を詳しく見る
Microsoft でイノベーションを促進


実績あるソリューションで成果を追求






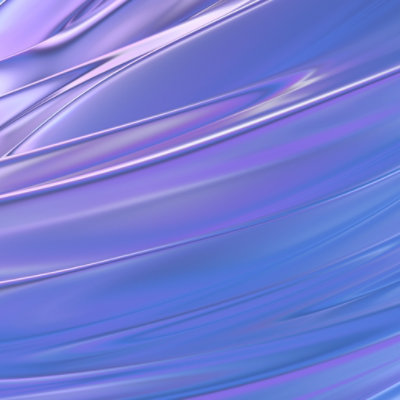

Microsoft をフォロー